音響監督、鶴岡陽太の「音響演出」を分析する(京アニ・シャフト作品を題材に)
目次
- 「音響監督」の具体的な仕事の内容
- 「演出」もしくは「音響演出」とは
- アフレコという作業の実際
- 音響監督、鶴岡陽太さんとは
- ダビングにおける音響演出の実際(『魔法少女まどか☆マギカ』より)
- コンセプチュアルにBGMを「つけた」ケース(『魔法少女まどか☆マギカ』TVシリーズ第1話、第10話より)
- 演出意図の考察1:重すぎるBGMを付けた理由とは?
- 演出意図の考察2:サウンドトラックに伏線を張る
- ダビングにおける音響演出の実際(『涼宮ハルヒの消失』クライマックスシーンより)
- コンセプチュアルにBGMを「つけなかった」ケース(『涼宮ハルヒの消失』より)
- 演出意図の考察3:ストーリー上の意味合いから演出を逆算する
- 演出意図の考察4:結末を知らないと理解できないことを音響演出で語る
- 演出意図の考察5:ストーリー上のコンセプトに劇伴を付けることが「無音」演出を選択させた
- コンセプチュアルにBGMをつける/つけないこと
- まとめ:「ダビング」による音響演出について
- アフレコにおける、鶴岡さんの音響ディレクション
- ナマモノとしてのアフレコ1:自分の責任において「OK」を出す勇気
- ナマモノとしてのアフレコ2:「これと同じことは二度とできないと思った」アフレコ
- ナマモノとしてのアフレコ3:アフレコという「場」
- 気付かせるディレクション1:役者とのディスカッションにより、自ずからキャラクターの意図に気付かせる
- 気付かせるディレクション2:敢えて抽象的な指示にとどめることで、役者も音響監督の想像を超えた場所を目指す
- 録音物としてのアフレコ1:再現性のあるもの、絶対値で揺るぎのないもの
- ナマモノとしてのアフレコ VS 工学的録音物としてのアフレコ
- 最後に:音響監督の音響演出について考えることは可能か?
- 関連記事
本稿は同人誌「多重要塞 vol.3」(当時の告知記事)に掲載した「アニメにおけるサウンド/ボイス演出と、ベストテイクを降ろす技術 ~ヒットメーカー鶴岡陽太のコンセプト志向~」を加筆・修正・改題したものです。
「音響監督」の具体的な仕事の内容
アニメの音響監督は、「音響監督」と聞いて僕らが思い浮かべるよりも、作品に、深く、多方面から関わっていく。
一般にテレビで流れているような映像はカメラで撮影すると同時に、マイクで音声も録音していることも多いが、アニメについては違う。もしビジュアルが完成したとしても、フィルムは無音の状態だ。だからアニメの中で鳴っている音は映像とは別個に、全くのゼロからつくらなければならない。そういう背景から、アニメ作品に対する音響監督のウェイトは非常に大きくなってくる。
音響監督の仕事は大別して以下の3つだ。
- 音楽家への劇伴(BGM)の発注
- アフレコ(声優による演技のレコーディング)の責任者
- ダビング(映像にBGMと効果音を吹き込む)
このように列挙しても、音響監督の仕事の全体像は見えてこないだろう。だからこの文章では、鶴岡陽太さんという音響監督の仕事を「音響演出」というキーワードを使って串刺しでピックアップしていく。それにより、音響監督という役職が、どのように作品全体の印象に関わり、またコントロールしているのかに、迫りたいと思う。
なお、この文章に書かれている内容は、各メディアでの鶴岡陽太さんに関する言及のほか、2012年11月4日に一橋大学で開催された鶴岡陽太さんの講演会「アニメに命を吹き込むこと」(一橋祭運営委員会主宰)での講演内容に多くを負っている。ただし、その解釈および表現についての責任は、筆者である僕にあることを、最初に断っておく。
「演出」もしくは「音響演出」とは
「演出」という、ちょっと使い方が難しい言葉がある。テレビアニメに関して言えば一本、つまり話数単位での映像の責任者の役職名であり、同時にその人間が行う作業そのものを指す言葉だ。話数の演出さんは、絵コンテをもとに、具体的な芝居の内容をアニメーターに指示し、成果物を随時チェックすることで、全てのカットの出来栄えに責任を負う。
アニメ作品が、映像と音響の2つの車輪を持っているとすれば、演出さんとは、映像面のディレクター・監督である。*1
一方、僕がこの文章のタイトルに挙げたように、音響監督も音響面で「演出」を行っている。音響監督は全ての話数のサウンド・音響面において、具体的な方向性を声優や作曲家に対して指示し、成果物を随時チェックすることで、映像の音響面の出来栄えに責任を負う。つまり音響監督とは、アニメ作品の音響面でのディレクター・監督として、話数単位での演出さんたちと対になる存在だ。
ここで「演出」という言葉の正体が徐々に形を取ってくる。演出とは、最終的に視聴者に伝えたい内容を、具体的にどのように表現するのかを決め、スタッフに作業を指示し、最後まで実際に実施するということだ。
たとえるなら演出は、山登りのルートを決定し、チームを登頂させる作業にも似ているかもしれない。地図を確認し、難所を避け、物資を調達し、手続きの整合性を取り、臨機応変にチームをコントロールする。
アニメ制作をはじめ、あらゆる集団作業がそうであるように、職能を持つスタッフは自分自身のセクションに意識が集中してしまっていることが多い。そういう場合に、全体を見回し、方向を指示する(ディレクションする)のが、映像面では演出さんであり、音響面では音響監督であり、そして作品全体に関しては、作品監督・プロデューサーであるというわけだ。
次のセクションからは、実際に音響監督の仕事について述べるとともに、より細かい「音響演出」の実際を見ていこう。
アフレコという作業の実際
さきほどは音響監督の仕事を「劇伴の発注」「アフレコ」「ダビング」に大別した。アフレコが実際にどのように行われているかについては、イメージをもう少し共有したい。
アフレコとはアフターレコーディングの略だ。実際の制作された映像(しばしば仮の映像であることもある)を上映しながら、音声を吹き込む演者、つまり声優がレコーディングスタジオの中で録音を行う工程だ。鶴岡さんによれば、アフレコは放映の2ヶ月ほど前に行われ、話数あたり、2.5~5時間程度を費やすという(TVシリーズの場合)。
アフレコを行うレコーディングスタジオについても説明しよう。スタジオは2つのスペースに分割されている。まず、声優たちがマイクに向かって演技するスペース、録音室がある。もう片方には音響監督と録音技師(ミキサー)、そして話数ごとの演出や作品監督が詰めているスペース、調整室がある。
その中でも音響監督はレコーディングに対してOK、NGを出し、必要に応じて演技のリテイクを指示する、アフレコ工程のディレクターが音響監督である。
アニメ制作スタジオ、マッドハウスのアニメ制作工程の紹介コンテンツから、音響監督の山田知明さんの表現を借りよう。
アニメーション制作で監督が全てを把握する役目なのと同じように、音響監督の仕事も一言で言えば「音響の全てを把握し、束ねる」ことなんだよ。監督は原画を全て描いたり全話の演出をするわけじゃないけど、方向性を決めたり全体をまとめるかたちで作品のバランスをとっているでしょう。音響監督も同じで、機材を使った収録作業はミキサーや録音助手の人がやっているけど、その方向をまとめたり、全体のバランスを取ったりする役目を担っている。たとえば「ここの音楽はどうしよう」とか「監督の意向に沿いつつも、もっとよくするにはどうしよう」といったことを自分なりに考える。
http://www.madhouse.co.jp/column/oginyan/oginyann_bangai_02_a.html (2014/11/8閲覧、強調は引用者)
音響監督は作品監督との打ち合わせを行い、脚本を読み込んでからアフレコに臨む。
ここで注意すべきは、上記で述べたように、録音機械を実際に操作しているのは録音技師(ミキサー)であり、音響監督ではないということだ。実際、音響監督を、その話数の演出や作品監督が兼ねることさえある。つまり音響監督とは、音響面での技術者ではなく、アニメ作品の方向性・伝えたいことを理解し、それをアフレコやダビングといった工程の中で、フィルムへ具体的に定着させる役職として、音響面での「演出」を担っているわけだ。
音響監督、鶴岡陽太さんとは
音響制作会社「楽音舎」を主宰する鶴岡陽太さん(以下、鶴岡さん)は、京都アニメーション制作の『涼宮ハルヒの憂鬱』『けいおん!』シリーズ、シャフト制作の『化物語』シリーズや『魔法少女まどか☆マギカ』など当代のヒット作・重要作に音響監督として深く関わった、いわば2000~2010年代アニメのキーマンだ。
以下に、代表的な作品を列挙した。
- 『魔法少女まどか☆マギカ』シリーズ(シャフト、2011~)
- 『けいおん!』シリーズ(京都アニメーション、2009~2011)
- 『境界線上のホライゾン』シリーズ(サンライズ、2011~2012)
- 『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズ(京都アニメーション、2006~2010)
- 『シゴフミ』(J.C.STAFF、2008)
- 『ブレイブ・ストーリー』(GONZO、2006)
- 『ケロロ軍曹』シリーズ(サンライズ、2004~2011)
- 『化物語』シリーズ(シャフト、2009~)
- 『神霊狩/GHOST HOUND』(Production I.G、2007)
- 『響け! ユーフォニアム』シリーズ(京都アニメーション、2015~)
鶴岡さんの音響演出の強度=説得力は、鶴岡さんの各作品に対する理解力・解釈の深さに由来する。その解釈の一部は確かに、打ち合わせの中で作品監督から示されたものなのかもしれない。しかし、鶴岡さんはそれを音響面から強力に裏打ちし、時にはビジョンを深く、鮮やかに広げるような作品作りをしていると思う。
これ以降の流れを紹介しよう。
前半では『魔法少女まどか☆マギカ』第1話および第10話のダビングと、『涼宮ハルヒの消失』で行われたダビングを、鶴岡さん自身の語りをヒントに対照的に比較する。鶴岡さんは講演会の中で「コンセプチュアルに劇伴をつける/つけない」という考えのもと、どのように作品の思想(最終的に伝えたいもの)を音響面から表現していったのかを、部分的ながら語ってくれている。僕らはそれを実際の作品と比較しながら、鶴岡さんの作品解釈のトレースを試みる。
後半ではアフレコ現場での鶴岡さんの特徴的なディレクションに迫る。現場での鶴岡さんは役者陣に対し「具体的な指示は出さない」ことで有名である。ここでは鶴岡さんと縁の深い声優である斎藤千和さん、沢城みゆきさん、安済知佳さんらの発言から、アフレコ現場での鶴岡さんのエピソードを確認する。そして鶴岡さん本人の解説により、これらがどのような狙いを持って行われているのかを考えよう。これにより、鶴岡さんが考えるアニメ音響と作品作りの特徴が、よりハッキリと浮かび上がってくるはずだ。
ダビングにおける音響演出の実際(『魔法少女まどか☆マギカ』より)
『魔法少女まどか☆マギカ』といえば、2011年1月から放映されたオリジナルテレビアニメである。
先の読めないストーリー展開と魅力的なキャラクター・ビジュアル・ドラマ立てでヒットを飛ばし、のちに劇場版も制作されたシリーズである。鶴岡さんはこのシリーズに一貫して音響監督として関わっている。
鶴岡さんは次でも述べる講演会の中で、「第1話のアフレコ時点で第9話までの台本を渡されていたが、この作品は非常に先鋭的なものだと感じた。のちにポピュラーな作品として受け入れられたのに驚いた」と述懐している。
なお、これと同様の発言は、劇伴を担当した梶浦由記さんとの対談でもされている。下記に引用しよう。
鶴岡 そもそも僕は、「この作品はすごく面白いけど、世の中に受け入れられるのだろうか?」と思っていました。ビジュアルも虚淵(玄)さんの脚本も素晴らしいんだけれど、「これ、みんなツラくないかな?」って(笑)。でも、いろいろな方からお力を貸していただいて、特にKalafinaさんのエンディング(「Magia」)を初めて聴いたときに「これは勝ったな」と思ったんです。
梶浦 あれは、最初に「バラードで」と言われていたのに「Magia」を作ってしまって(笑)。バラードの”バ”の字もなくて、普通だったら「何やってんだ!!」って感じですよね。
(Fiction Junction CLUB会報 Vol.31(2016年8月))
「FictionJunction CLUB」終了に関するご案内
鶴岡さんの中でも本作は、その特異な内容でもって印象的な作品だったようだ。では、鶴岡さんは本作の音響演出をどのようにディレクションしたのだろうか。
次のセクションでは、2012年11月4日の鶴岡さんの講演会「アニメに命を吹き込むこと」の部分的な再現のかたちをとって、第1話の渡り廊下のシーン、そして第10話の印象的なシーンにつけた同様の劇伴の意図について、鶴岡さんの言を交えながら解説する。
なお、説明の都合上、以降では本編テレビシリーズ第10話までのネタを割るため、未見の方は注意して欲しい。(以下の「講師」とは鶴岡さんを指す。)
コンセプチュアルにBGMを「つけた」ケース(『魔法少女まどか☆マギカ』TVシリーズ第1話、第10話より)
講師はPCを使い、用意してきた映像をかける。前段では、音響での演出に決まりやセオリーなどはないと講師は述べた。しかし、特にコンセプチュアルな必要に応じてBGMをつけたり、逆につけなかったりしたケースがあるという。ここで説明するのはコンセプトに応じてBGMを「つけた」ケースである。
《シーンA》

(『魔法少女まどか☆マギカ』TVシリーズ第1話より、主人公まどかが謎の転校生ほむらを保健室に送り届けるシーン。BGMはうつろなベルの音の沈鬱なテーマ。まどかは場を保たせるように話題を繋ぐも逆効果となり、ほむらの顔はどんどん険しくなっていく。渡り廊下にさしかかったところでほむらが振り返り、BGMも終わる。)
講師笑いながら、「Too much, too heavy(過剰、過重)です。普通は第1話の冒頭でこんなBGMはかけません」。しかしこれは、次にかけるシーンと対応します、と言って講師、更に別の映像をかける。
《シーンB》

(TVシリーズ第10話終盤。ほむらのモノローグ「繰り返す、私は何度でも繰り返す」から始まるシークエンス。バックでは第1話の渡り廊下のシーンで流れた、あの沈鬱なBGMが鳴り始める。映像はここで第1話、魔法少女のほむらとまどかが出会うシーンに戻ってくる。BGMが終わると同時に、OP映像「コネクト」での特殊ED・スタッフロール。)
「これいいですよねー。僕はこの組み合わせができた時点で『勝った』…まぁ、そういう手応えを感じました。これが、僕の『合う・合わない』や趣味ではなく、コンセプチュアル・必然性に従ってBGMをつけたという事例です」と講師は結んだ。
演出意図の考察1:重すぎるBGMを付けた理由とは?
『魔法少女まどか☆マギカ』テレビシリーズ第10話は本編のいわばバックストーリー(状況の背景・登場人物の過去を語る)にあたる。第1話以前に起こった出来事を説明し、その最後のシーンを第1話冒頭に接続することで、ほむらの存在というストーリー最大の謎を明らかにする、シリーズの最重要話数だ。
テレビシリーズのBlu-rayディスク第5巻のブックレットの中で、オープニングテーマ曲「コネクト」を第10話のエンディングに流すアイデアを出したのは新房昭之監督であることが明かされている。一方、1話および10話の該当シーンのサウンドトラックにあの沈鬱な鐘の劇伴「Puella in somnio」(作曲:梶浦由記)を流したのは、鶴岡さんの判断だ。
鶴岡さん本人は、ここでの意図を具体的な言葉で説明することはなかったが、その意図するところは例証によりかなり明確である。
本人が述べる通り、シーンAで流れる陰鬱なBGMは、お話の冒頭に持ってくるには、一般的に最も適しているとは言えない。映像はほむらの表情も含めて示唆的ではあるが、それが何を示すものなのかは視聴者には分からないため、ほむらからまどかへの異様な圧迫感を示すに留まることだろう。しかしこの違和感は視聴者への強力な「フック」として働くことになる。
一方、シーンBでも全く同じBGMが使われているものの、ここでの視聴者への聞こえ方は全く異なる(これが重要だ)。ほむらのバックストーリーが充分に語られた今、シーンAでほむらがまどかの受け答えに対し、なぜあのような態度をとってしまったのかも、今や視聴者には決定的に明らかである。ここでうつろに響くベルのBGMはほむらの孤独、悲しみ、諦めであると同時に、あたかも運命を告げる鐘の音のようにも聞こえてくるのである。
演出意図の考察2:サウンドトラックに伏線を張る
更に補足しよう。
ここでのシーンAとシーンB、視聴者が視聴する順序はA→Bだが、物語の時系列ではB→Aである。間に9話分を挟んで時間軸が前後する、曲芸のようなストーリー展開だ。
重要なのは、ここでの音響演出はここでの時間の反転の説明を補助しているということだ。つまりシーンAで流れたBGMは、シーンBから視聴者の意識を冒頭シーンAに繋ぐためのフック、いわば、記憶への「しおり」なのである。
鶴岡さんは、状況・シチュエーションにマッチしないBGMを、シーンAへ意図的に配置した。そしてこのBGMは、シーンAにおいては、視聴者が理解すべきまどかやほむらの感情を補足・強調したり、シチュエーションを盛り上げたりするために配置されたものではない。であれば、「ストーリーや作品全体を貫く仕掛け・コンセプトを伝えるために配置されたBGMである」としか表現できないだろう。
つまりこれは、シーンBがシーンAのほむらの反応を説明すること、そしてこの10話が1話冒頭に繋がるものであることを、視聴者の無意識に残された「違和感のしおり」へ訴えることで、おのずから悟らせるための演出だったということだ。鶴岡さんは映像の音響面つまりサウンドトラックに、いわば「伏線を張っている」のである。
ダビングにおける音響演出の実際(『涼宮ハルヒの消失』クライマックスシーンより)
次のセクションでは、『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズ劇場版『涼宮ハルヒの消失』(2010)のワンシーンを題材に、鶴岡さんが劇伴をつけなかったケースを追う。
『涼宮ハルヒの消失』といえば、テレビシリーズ第一作と第二作の間を埋める人気エピソードを映像化した劇場作品で、人気キャラクター長門有希と主人公キョンとの関係にスポットが当たる。
こちらで説明されるのは『魔法少女まどか☆マギカ』とは反対に、敢えてBGMをつけなかったケースとなるが、その意図は同種のものだ。つまり個々のシーンに対してその劇伴がマッチしているかどうかではなく、作品全体が最も伝えたい部分つまりコンセプトに従って判断しているという意味で、である。
コンセプチュアルにBGMを「つけなかった」ケース(『涼宮ハルヒの消失』より)
<このセクションには、『涼宮ハルヒの憂鬱』TVシリーズ最終話、および『涼宮ハルヒの消失』のネタバレが含まれます>
講師、PCを使い映像を流す。「これ始めると長くなりますよ」。

![涼宮ハルヒの消失 限定版 [Blu-ray] 涼宮ハルヒの消失 限定版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51TJc0iVkHL._SL160_.jpg)
(『涼宮ハルヒの消失』より、後半のクライマックスシーン。BGMは無い。
クラスメイトがSOS団のメンバーを知らないどころか、当のメンバーも今や全くの別人として生きていることを知ったキョンは、もはや自分は元の世界に戻れなくなってしまったのではないか、という絶望に襲われる。
突然、誰も触れていないはずの部室のPCに電源が入り、文字だけがひとりでに表示されていく。(C:後述)最も頼りにしているSOS団のメンバー、長門の名前が表示され、キョンはPCにかじりつく。ハルヒからの言葉も耳に入らない。
PCが点いてからは、ブラウン管がうなる「ブーン」という音だけがずっと低く鳴っている。キーボードの音も無い。表示された言葉に返事するかのようなキョンのモノローグ。しかしキョンの期待とは裏腹に、このメッセージを残した長門はキョンに対し、逆に非常に重い決断を迫るのだった。(D:後述)3分ほど、キョンのモノローグとPC画面を使った映像が続くが、BGMは一貫して流れない。)
講師「『これ保(も)たないだろ』*2と普通は考えます。誰か文字を叩いているわけでもないので、キーボードの音も無い」。
ここでは、ある意図をもってBGMをつけなかった。試しに、このありあわせの音楽を映像に乗せてみよう、と講師はPCに映像プレイヤーと音楽プレイヤーを同時に立ち上げる。映像プレイヤーでさきほどと同じ映像を流す。映像が(C)のタイミングで音楽プレイヤーを使いBGMを再生し始め、それは(D)のタイミングまで流れ続ける。
BGMは弦楽器を主体とした「安心」を感じる音楽だ。会話が佳境を迎えると音楽の調子も合わせて高まり「予感・決断」を、最後には「不安」を示唆して収束する。プロの手による生のダビングである。
BGMがついたことにより、こちらにはその出来事が、世界の命運が懸かるほどの重要なものであること、キョンが会話している相手がとても頼りになる相手であること、などがありありと伝わってきた。
しかし劇場公開された実際の映像では、このBGMはついていない。講師「いいですねー、自分でやってても『これ良いんじゃないの?』と思ってしまいました。ちょっとしたSF映画みたいになったでしょう。
ただこれは『こう見えちゃいけない』シーンなんだ! こう見えるくらいなら、いっそ保たないほうがいい」。
講師はこの日、最も強い調子で述べた。
演出意図の考察3:ストーリー上の意味合いから演出を逆算する
以上が、コンセプトに基づいてBGMを「つけなかった」シーンだという。鶴岡さんはこのように2つのテイクを並べて示したものの、やはりその演出意図を言葉で説明しようとはしなかった。であるならば、ヒントをもとに考えるしかない。
なぜここで「いつも頼りになる長門が助けにきてくれた!」という演出を鶴岡さんは選択せず、更には「してはいけないのだ」という確信さえ持っているのか。
結論から言えば、この音響演出は『消失』に仕掛けられた物語上のトリックの伏線になっている。TVシリーズ最終話『涼宮ハルヒの憂鬱Ⅵ』では、遂に退屈な世界に飽きたハルヒが、無意識に、あわや宇宙自体のあり方を根本から書き換えてしまう「世界改変」直前にまで至る。
そして、TVシリーズ最終話に続く『消失』では、ある朝キョンが目を覚ますと、SOS団の面々が赤の他人となり、ハルヒに至ってはもとからいなかったことになってしまっている(タイトルの「消失」の意味)という、やはり世界改変に関するストーリーである。
キョンは大いに動揺するものの、以前の経験から、恐らくハルヒがこの世界改変を起こしたのではないかと推測する。もちろん、視聴者もそう考える。しかし、違うのだ。
改変後の寂しい世界でキョンの心の支えとなるのは「長門有希」である。世界改変前は無感情・無表情の万能ヒューマノイドであった長門は、改変後の世界では単なる女子高生「長門有希」となり、更にはキョンに対して積極的なアプローチさえ行うのだ。
劇中では最終盤に明らかになることだが、実は、長門はキョンとの出会いによって生じた、友情・保護欲とも恋ともつかぬモヤモヤした感情(一般的には恋愛感情と呼んでも差し支えない)を非常に持て余していたのである。
クリスマスを控えた深夜、遂に抑えのきかなくなった長門はハルヒの世界改変能力を奪い、キョンの記憶だけを残したまま、世界を一から創造し直してしまったのだ。
すなわちこのエピソードの真犯人は、ハルヒではなく長門なのだ。
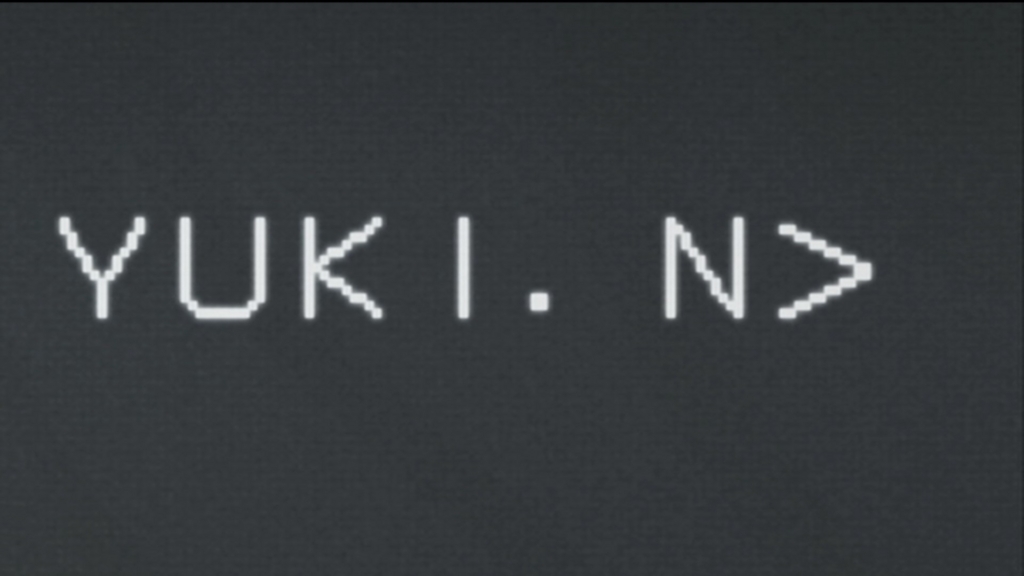
演出意図の考察4:結末を知らないと理解できないことを音響演出で語る
さきほどのシーンに戻って、具体的に説明しよう。TVシリーズを通じてキョンとハルヒはお互いに、明らかに好意を持ち始めている。長門はキョンと親しいハルヒをキョンの人生から消し去り、また自身はキョンと生身の女性として出会い直すことで、ハルヒからキョンを、いわば「奪い取ろうとする」。
とはいえ、世界改変を起こす前に、長門の理性はセーフティーネットを仕掛けていた。それこそ、さきほどのシーンに登場した自動プログラムである。もしキョンが本当に元の世界を望み、リターン(回帰)キーを叩いたならば、改変後の世界をキョンは一人脱出することができるのだった。
キョンはキーボードの前でひとしきり思い悩んだのち「そうだ、俺はたとえハチャメチャであったとしても、元の楽しい世界を選ぶぜ」とリターンキーを叩き、元の世界へ戻っていく。しかしここまで先取りして書いてきたバックストーリーを考えれば、ここでは長門とキョンの思いが完全にすれ違ってしまっている、ディスコミュニケーションを起こしていることは明らかだ。
実は長門の残した対話式プログラムが問うているのは「新しい世界で新しい私と一緒に暮らしてくれるかどうか」という、いわば愛の告白なのだ。しかし、キョンにはそれが告白であることさえ伝わっていない。そして大事なのは、それは視聴者さえ例外ではないということだ。
僕ら視聴者はキョンの全力疾走とファインプレーによって一縷の救いに辿り着いたスペクタクルに乗せられており、この時点では長門のメッセージの真意には辿り着くことはできないのだ。
この誤解が本作の「メイントリック」にあたる。このシーンで視聴者は「ヒロインの真意に鈍感にも気付かず、傲慢にも傷付ける」主人公の、知らず共犯者にされてしまうところが、本作の批評的なポイントだ。*3
ところが実は、音に、音響演出にこそ、仕掛け・伏線が施されていた。
演出意図の考察5:ストーリー上のコンセプトに劇伴を付けることが「無音」演出を選択させた
ここまでの文脈に沿って考えれば、このシーンの表側には「今まで存在していた世界、そして再作成された世界の命運が掛かった決断のシーン」という流れがあり、そして裏側には「ごく普通の女の子の告白のシーン」という流れが同時に存在している。
もし表側のシチュエーションに対してBGMをつけるのであれば、スペクタクルを焚きつける、たとえば鶴岡さんが実際に流したような、いかにも劇場版という感じのゴージャスなBGMであっても良いのかもしれない。しかしシーン単位のシチュエーションに対してBGMをつけたことで、視聴者の意識から裏側の要素を違和感なく塗り潰してしまうだろう。鶴岡さんはそれだけは避けたかったのではないだろうか。
終盤、長門の恋愛感情はキョンの無理解と、そして皮肉にも自分自身の手によって「無かったこと」にされてしまう。しかし、エンドロール後には物語上の小さな救いが用意されている。それは、霧散したはずのキョンへの思いが、長門の中にどういうわけか残っていることを示唆する短いシーンだ。
鶴岡さんの音響演出も、年相応の少女としての長門を描くという作品全体の色調に沿うかたちで、PC越しに会話するシーンには、大仰なBGMはつけないどころか、環境音のみで演出した。初見の視聴者であれば、シーンに隠された二重の意味を読み取ることは不可能だろう。
しかし観終わったあとであれば、自然ともうひとつの意味に辿り着くことが可能になっている。鶴岡さんはこのシーンに敢えてBGMをつけないことで、「長門の感情」という、ストーリーという大きな力によって非常に抑圧、ともすれば圧殺されてしまう、しかし作品としては最も重要なコンセプトのひとつに寄り添っているように思う。
コンセプチュアルにBGMをつける/つけないこと
ここまでで分析してきた『涼宮ハルヒの消失』、そして『魔法少女まどか☆マギカ』1話/10話で行われた音響演出は、同じような2つの働きを担っていることを確認してきた。
まず、シーン単位のシチュエーションに対してはマッチしないBGMを敢えてつける、もしくはつけないことで、そのシーンの重要性をさりげなく表現し、伏線を張ること。
もうひとつは、ワンシーンの表現よりも作品全体のコンセプトの表現を優先させることで、シーン単位もしくは話数単位での意識を越えた表現を、サウンドトラックに織り込むことだ。メインスタッフとして初期段階から作品にコミットしている音響監督は、先の例のように、テレビシリーズであれば話数の区切りを越えた表現を仕込むことも可能となる。
まとめ:「ダビング」による音響演出について
今回はメインで扱ってはいないが、鶴岡さんは効果音や環境音によって、映像に非常にリアルな現前性を持たせる音響監督である。
TVアニメの傾向として、映像が全体的が「リアル」つまり実際にあり得るかのような映像作りに舵を切っていると、個人的には感じる。たとえば3DCGを補助に使い、立体表現として整合性を持たせたレイアウト(絵の構図取り)や、フォトリアルな背景美術、シリーズを通して背景美術やレイアウトの整合性をとるための美術設定、実際の土地や風俗をモチーフに取り込んだ舞台設定などだ。
その中で鶴岡さんは、カットが切り替わるたびに、建造物の材質や構造に応じて雨音の響きを、車種によってエンジン音を変更したりといった小さな音響演出の積み重ねによって、音響面から映像のリアリティの底上げに寄与してきた経緯がある。
鶴岡さんの音響演出は、そういうテクニカルな側面や、次でも述べる特徴的なアフレコのディレクション(役者のポテンシャルの引き出し方から「鶴岡マジック」とさえ言う人もいる)に注目されることが多いが、作品コンセプトの深い理解や、スタンダードでありながら丁寧な読解から生まれる、「合目的」的な音響演出にも、同じく着目すべきだ。
今回、細かく例証してきたことによって、音響監督というポジションが、どのように作品全体のトーンや深みを、音響面から作り上げていくのかという部分の一端を、垣間見ることができると思う。
アフレコにおける、鶴岡さんの音響ディレクション
このセクションでは、アフレコでの鶴岡さんの特徴的な音響演出、つまり声優・役者に対するディレクションについて述べよう。
アフレコをディレクション、つまり「監督する」ということは、鶴岡さんにとってどのような意味を持っているのか。鶴岡さんはアフレコを「ナマモノでもあり、録音物でもある」という両面からコントロールしようとしているように思う。次の段からは、それを検証していこう。
まずはアフレコの「ナマモノ」性について追っていこう。アニメ作品の配役では、毎回オーディションが開かれる。デビューしたての若手実力者の出演作が一気に増えるのは、オーディションを通した実力主義が大きく関係している。オーディションの手配も音響監督の仕事のひとつであり、現場の監督としての立場から、配役に対する発言力も自然と大きくなってくる。
鶴岡さんは講演会で次のように、役者の作品への起用について語ってくれた。
僕ら音響監督は「知らない奴のことを聴くのが仕事」だから、役者の「全体のパフォーマンスを知りたい」と思っている。このパフォーマンスというのは声質のことであったり、「喋れるか喋れないか」(機転や滑舌など喋りの素養のことか)であったりする。ただ「まぁ、声はどうにもならないから」。逆に「知っている奴なら狙いを持って起用」している。
オーディションは音響監督にとって、有望な役者をピックアップするための開拓地だ。数百人にのぼる音声サンプルを聴き、個々人の能力を見定め、作品に対してどのような貢献をしてくれそうなのか、他のメインスタッフと相談しながら判断する。
一方で鶴岡さんは、既に一緒に仕事をしたことがある役者であれば、起用意図があるという。では、鶴岡さんの言う「狙いを持って起用する」とはどういうことだろう。鶴岡さんは次のようにも言う。
アフレコをして最上なのが「思ってたのと違うけども良い」で、最悪なのは「思ってたのと違うし、悪い」だ。このときの僕の善し悪しの基準は「作品の持つ面白さの方向性にのっとっているのかどうか」になる。
つまり、鶴岡さんが役者を起用する際の判断基準は「作品の持つ面白さの方向性に貢献してくれそうか」という部分になってくる。
これはこの文章の前半で鶴岡さんが「コンセプチュアルにBGMをつける/つけない」という部分で行ってきたことと同じである。「作品の持つ面白さ」とは、作品が視聴者に最終的に伝達する感覚の最も基軸となる概念、つまり「コンセプト」に等しい。
では鶴岡さんはアフレコの中でどのようにして、そのコンセプトを実現しようとするのだろうか。
コンセプトをそのまま実現しようとしても、アフレコには不確定要素が多い。なぜなら、アフレコとは工学的なレコーディングであると同時に、役者たちの演技の「セッション」であり、その場その場の雰囲気や、それまで積み重ねてきたもの、役者たちのシナジーによって、出来上がってくるものは別物のように変わってくるからだ。
次からのセクションでは、アフレコの「ナマモノ」性について、鶴岡さんの発言や、関わりの深い声優さんたちの発言から、確認していこう。
ナマモノとしてのアフレコ1:自分の責任において「OK」を出す勇気
鶴岡さんは自分自身の作品理解を土台に演出プランを立ち上げ、完成に至るまでのビジョンを持ってアフレコに臨んでいる。しかしそれはアフレコにおいて、単にワンマンであるという意味ではない。
もし役者が出してきた回答が、アフレコに際して自身が考えていた全体の演出方針と違っていたとしても、作品の最終的に目指すところの面白さ・コンセプトと合致しており、かつ想定を超えているのならば、そちらを取るという。
しかし、それは言うほど簡単なことではない。
アフレコは演技をデジタルデータに録音する工程であると同時に、役者同士の化学反応によって、想定していたもの以上のパフォーマンスと演技を生み出す、ジャズの即興音楽のような側面がある。
その中で、何が正解なのかを判断するのは、たとえば作品を理解し、役者を起用するといった、アフレコという本番までに行うべき仕事とは、また別の力が必要だという。鶴岡さんは講演会で次のように言った。
音響監督には「OKを出す力」が必要だ。それは一種の「度胸」だし、録音で「ベストを出すまでの力とは別の力」だ。
「OK」とは映像/音声の収録時、その時の演技(テイク)の録音を映像に反映させるという判断をメンバーに知らせる際のかけ声のことだ。実写であれば、そのテイクをOKと判断するのは監督、すなわち作品監督の仕事だ。しかしアニメでは音響監督が行う。
自分の考えていたルートで進んだアフレコであれば、それを満たす演技が上がってきた場合に「OK」を出せば良いだろう。
しかし、役者の解釈で上がってきた「良さ」を、作品のコンセプトに照らして「善し」とするのかどうか。その判断を、音響監督は引き受ける強さ・度胸が必要なのだとも言うのだ。これはアフレコを「ディレクションする」ということの心構えの話でもあり、またアフレコの「ナマモノ」性を積極的に引き受けることで、一貫性を保ちつつも、ベスト以上のベストを出すための技術論の話にもなっている。
ナマモノとしてのアフレコ2:「これと同じことは二度とできないと思った」アフレコ
そんな鶴岡さんにも、特に忘れられないアフレコがあるという。
今までやってきて「失敗含めて全て『OK』と考えている」が、二度とできないアフレコはある。それが『魔法少女まどか☆マギカ』TVシリーズの第10話だ。アフレコに際して僕は、もし『こじれ』たらパートごとに録ろうと思っていたが、斎藤(千和)さんはすごい、予想外にうまくいった。だが二度とはできないと思った」。
だから、総集編となる劇場場の制作に際し、新房昭之監督に10話だけは録り直しはやめてくれと言ったほどだ。(注:TVシリーズ第10話はストーリー上の重要回。TVシリーズの総集編にあたる劇場版では基本的にアフレコをし直している。)
ここで「パートごとに録る」という言葉が出てきた。少し補おう。
TVアニメのアフレコではまず、一度最後まで通して芝居をする。これを「テスト」と言う。次にもう一度、本番テイクを録音する。更にデータの取り回しを良くするため、部分的に録音しなければならないシーンや、NG部分、調整室のメンバーがもう一度録りたい部分を、更に録音するという手順だ。
鶴岡さんは勿論、作品監督の新房さんも、第10話の脚本が難しいことは承知していた。(Blu-ray第5巻の脚本家虚淵玄さんとの対談でも、新房監督は「1時間分くらいの密度がある脚本でしたよね。映画並みのボリュームがありました」と述懐する。)それは映像面での密度の話でもあるが、また役者にとっては幅広い演技を求められる難易度の高い脚本だったということだ。
第10話は先に説明したように、語りの時系列が前後したり、時間が突然経過したりというシーンが頻出する。30分で一気に録り切るタイプのTVアニメのアフレコでは、特に演技や感情の切り替えや盛り上げ方が難しくなってくることは想像に難くない。
そのため、鶴岡さんは「パートごと」つまりイレギュラーな方法ではあるものの、話数の前半・後半にアフレコを分割し、合間で演出や芝居の方針を調整するというプランを用意していた。
しかし、この話数のメインキャラクター暁美ほむらを演じる斎藤千和さん*4は、それをやってのけてしまった。
ナマモノとしてのアフレコ3:アフレコという「場」
音響監督はもちろん、作品全体を見通した音響演出プランを持っている。ただし、作品コンセプトに合致した高いパフォーマンスを役者が提示した場合には、事前のプランを修正することは、むしろ鶴岡さんにとって喜ばしいものだということを、鶴岡さん自身の発言から確認した。
しかし『魔法少女まどか☆マギカ』10話での斎藤千和さんの卓抜した演技は、鶴岡さんの手の内を離れ、ブラックボックスのようなものになってしまった。それは同じメンバーをもう一度集めたとしても、それ以上のものを作るのは難しいと判断したということだ。つまり10話の演技が色々な要素の影響を受けて作られた「場」の産物であるということを、鶴岡さんは知っていたということではないかと思う。
この第10話のアフレコを振り返って、斎藤千和さんと、主人公まどか役の悠木碧さんは次のように述べている。
悠木 みなさんに「一〇話はすごかったね」って言っていただいて、物語的にも盛り上がるところだったんですけど、まどかとしてキャラクターに入り込んでいる私としては、一〇話が特別だったわけではなくただ、『まどか☆マギカ』という作品を演じるにあたって、その歳の子たちの感じるリアルな痛みを表現したいということを思っていただけなんです。そういう意味では、一〇話は痛みに特化したところだったし、表現としても幅広く演じられたのかなと思います。
私、お芝居している時に本当に白熱すると、記憶が飛んでしまうくらいになるんです。
(略)
――一方、斎藤さんはほむらとして、ここに来るまでに色んなものを溜め込まれてきましたよね。
斎藤 そうですね。我慢、我慢の連続でした(笑)。でも。私もやっぱり碧ちゃんと一緒で、一〇話だから特別に何かをしたというつもりは一切なくて、今までやってきたことの積み重ねがあるからこそ、一〇話が特別なものに感じるだけだと思うんです。
(略)
ただ、彼女が抱えているものは最初から少しずつお芝居の中で小出しにしているんですよ。一回最後まで見て、また一話から見直してもらえれば、違うほむらの揺れ方を感じていただけるようなお芝居をしようと心掛けていました。
(ユリイカ 11月臨時増刊号『総特集*魔法少女まどか☆マギカ』、25P)
アフレコという場が、単なる技術的な総体ではなく、役者それぞれのキャラクターとの対話や、それまでの積み重ねから生まれた熱量のようなものの上に拠って立っていることの一端が伝わってくるような発言だと思う。
鶴岡さんは、この斎藤千和さんの演技への賞賛を、次のような音響演出で、言葉を使わずとも雄弁に示している。Blu-ray第5巻のオーディオコメンタリーから、斎藤千和さんの発言を書き起こした。
(第10話、銃口をまどかのソウルジェムに向けるほむら)
斎藤 だから、やりたくないことでも、ここのところもそうだけど、うーん…
悠木 ここ、ここの叫びが痛くて…
斎藤 そうだったの。これはね、ほんとにあのわたし、公式ガイドブックの取材で話して、ちょっと重複しちゃうかもしれないけど、あーちゃんは知ってるけどね?
悠木 うん
斎藤 ほんとにもう、「ウーッ!」ていうあの叫び声が、ほんとにただの、声にならない叫び声っていうか呻き(うめき)、というか
悠木 そう、叫び声
斎藤 で、やらせて頂いて、すごく嬉しかったのが、鶴岡さんが、SE(効果音)を入れずにいてくれたこと!
悠木 うん、うん
斎藤 ほんとに嬉しかった、わたしの声に任せてくれて、多分台本ではSEで「バーン」だかなんだかわからないけど、
悠木 (脚本だと)そうなってました
斎藤 そういう音が、入っていたものを消してくださったことが、もう、わたしがみんなを信頼したように、みんなもわたしを信頼してくれるんだ、っていうこの気持ちがすごく、嬉しくて。ほむらが戦い、続けるのもそうだけれど……
悠木 うん。うん
斎藤 やっぱ頼ったほうがいいなって思ったね!(笑)
悠木 そうですねぇ、ほんとに。みなさんの力を感じてっていう風にお芝居ができる場があって、素敵だなと思って
なお、最終稿が載っている脚本集を参照してみると、悠木碧さんの言う通り、このシーンは次のような描写がされている。
ほむら「……ッ」
嗚咽を噛み殺しながら、まどかのソウルジェムに拳銃の狙いをつけるほむら。
廃墟に、銃声が轟き渡る。
(魔法少女まどか☆マギカ The Beginning Story、角川書店、141P)
*5
ここまで鶴岡さん、そして鶴岡さんと縁の深い役者の発言を追うことで、鶴岡さんがアフレコをどのような「ナマモノ」として扱っているのか、という部分に着目してきた。
鶴岡さんは作品コンセプトに沿って音響演出プランを考案し、それを実現するための役者を作品に呼び込む。しかし実際にアフレコにおいては、自身の音響演出プランから逸脱した演技も、作品コンセプトに沿ったものであれば「善し」として、その選択については自身の責任において引き受けていく。
そして特に『魔法少女まどか☆マギカ』第10話では、アフレコという現場が生み出すものを尊重し、自身の音響演出プランに組み込んでいったことを確認してきた。
気付かせるディレクション1:役者とのディスカッションにより、自ずからキャラクターの意図に気付かせる
アフレコがいくら不確定要素の多いものだからといって、行き当たりばったりのディレクションをするしかないというわけではない。事前に考えていたプランを超えたパフォーマンスをアフレコへ呼び込むために、鶴岡さんは役者さんたちに対して、実際にどのようなディレクションをしているのだろうか。
鶴岡さんは、作品のイメージを役者たちと共有するために、作品自体についてディスカッションすることも多い。そのため、京都アニメーション作品やシャフト作品のメイン声優へのインタビューでは「音響監督と話し合ってこういうプランにした」という発言が頻出する。
たとえば『響け! ユーフォニアム』1期でヒロインの高坂麗奈を演じた
安済知佳さんが、鶴岡さんと作品解釈についてどのようなやり取りを行ったかを、具体的なエピソードで語ってくれている部分がある。
安済 (略)居残りといえば、久美子に「滝先生がこの学校に来るって話、私、お母さんから無理矢理聞き出して」と語るときも、ひとりで居残りでした(笑)。あのシーンでは、音響監督さんから「麗奈の足をよく見て」と言われたんです。見たら、ちょっとモジモジしてるんですよ。
(略)
さらに音響監督さんからは、「なんでモジモジしていると思う? この気持ちを初めて人にはなすことが恥ずかしいってだけじゃない。もっとガールズトークをして」と言われました(笑)。後にも先にも、麗奈のガールズトークが聴けるのはあそこだけですね、居残りになるほど苦労したのに、ガールズトークっぽく演じてみたら一発でOKでした(笑)。
(略)
心を許した久美子と接するときや滝先生を見つめるときの麗奈は、想像以上に乙女なんです。なのに、私がそれを汲み取れないときがあったみたいで。あなたはトランペット一筋でしょ!といおう、勝手な思い込みが邪魔しちゃうんです。
(TVアニメ『響け! ユーフォニアム』オフィシャルファンブック、宝島社、37P)
役者との作品・キャラクター解釈に関するディスカッションは、アフレコによって目指すところの作品の面白さの着地点・イメージ・ビジョンを役者と共有することで、役者のパフォーマンスを最大限に引き出すために行っていると考えられる。
音響監督は一般に「アフレコの現場監督」とよく言われる。作品監督や各話演出さんが考えているゴール地点を「もっと強く言って」「ここは悲しそうに」といった具体的な指示に変換して役者に伝えるという役割からだ。
しかし鶴岡さんの場合、単に指示を具体化するだけではなく、上記のように、役者自身に気付かせ、考えさせるようなディスカッションを行っている。その場限りの指示だけではなく、シーンごとにキャラクターが何を考え、それが作品全体にどう影響しているのか、意見を交換し、役者自身に気付かせ、改めて考えさせるのだ。
これにより、役者と音響監督の意図するところがコンセプトのレベルですり合わせされ、演技のベクトルが揃っていく。つまり、スタッフ全員が同じゴールを目指して進んでいくことができるのである。
気付かせるディレクション2:敢えて抽象的な指示にとどめることで、役者も音響監督の想像を超えた場所を目指す
更に例証しよう。
鶴岡さんとの仕事も長い、沢城みゆきさん*6は、自身のラジオ番組で鶴岡さんと、次のような会話をしている。アニメのアフレコ未経験の俳優と、キャリアのある声優とで演技に関する指示を意識して変えることは無い、という話題に続く部分を抜書きした。
鶴岡:逆にそうだね、それはまぁ人によってスタイルが、多分だから、普段俺がやってるスタイルってのが、きっと汎用性(があるのかもしれない)、汎用性って言うと変だけど
沢城:あぁ、なるほど
鶴岡:たとえばあなたたちに何か言う時でも、あんまり具体的なことをそんなに言わない…
沢城:言わないです!
鶴岡:極力…
沢城:言わないです!
鶴岡:うん
沢城:本当に
鶴岡:それがまぁ、そういうことで
沢城:うん
鶴岡:双方どちらにも通用するのかなって。そう、あんまり自分のスタイルを変えずにいけるんじゃないのかな。これね、多分具体的なことを言ってると、やっぱりある程度変えないと、難しいと思うんだよね
沢城:はい、そうですね。すごく、鶴岡さんって、こう、こっちまでは来ないというか、見えるところまではツツッと来てくれるんですけど、的確なことというより、ヒントをくれて帰っていく人みたいな。「あー、って言われたけど、そのヒント貰ってどうしようかな」っていう範疇はまだこっちにあるというか
鶴岡:うん
沢城:でも、本当に言う人って「語尾を上げてください」みたいな明確な指示であったりとか、絶対こう…、絶対譲ってもらえないところがあったりするので、それは確かに汎用性、そうかもしれないですね
鶴岡:多分ね、そういうアプローチだと、局面局面においてね。「中身的にはこういうことなんで考えて辿り着いてください」と
沢城:そう、そうですね!(笑) 時々なぞなぞみたいなダメ出しもあって、我々の間で話題になるんですけども。私が今までで鶴岡さんに言われたダメ出しの中で、オォーって思ったやつが「えー、沢城、もっとのりしろを多く」って言われたことがあって…。
「ハ…ハイ!」って言っちゃったけど、鶴岡さん出てってから「のりしろ多くってどういうことだろう?」と思って自分の中を一杯探して、やったのがありましたけども…(笑) そんな感じなんですよ、みなさん? ふふふ
鶴岡:(吹き出すような笑い。)…わかれよ!
沢城:ふふ、あはは。…もう、外も大爆笑ですから、鶴岡さん、ほんとうに
(沢城みゆきと12の夜 #11 (2010/05/08))
鶴岡さんが役者に対して、具体的な指示ではなく、方向性・ヒントだけを示すようなディレクションをしていることは有名だ。
声優の福山潤さんとの対談でも、その特徴的な言い方について、福山さんが『∀ガンダム』(1999〜2000)で初めてリアルな人間の役を得たときの話で触れられている。
福山 当時の僕は、そもそもアニメで人間のキャラクターを演じたことがなくて、キースが初めての等身大の人間の役だったんです。当然デフォルメではないリアルな芝居を求められたのも初めてで、手持ちの武器が何もない状態でした。毎回「うわ、何もできない!」と思い知らされた作品でした。
鶴岡 でもその丸腰な感じ、武器のない感じも無垢で良かったんだよ。何しろ滑舌がよくて口は回るんだから(笑)。
福山 そうそう(笑)。それ以来鶴岡さんとご一緒するたびに言われていたのが「誠意を持て」と「勝算はあるのか」のふたつでしたね。
鶴岡 福山は口から言葉を発する能力がズバ抜けていて、とにかく流暢。だからこそ、たまにはちょっと止まって考えてみろと(笑)。
福山 あはは。鶴岡さんのアドバイスってすごく絶妙で、答えそのものをポンと提示してくれるわけじゃないんです。僕のやりたい芝居のプランが作品や役柄と合っているか、あるいは考え方として適切かどうかも見てくれている。そういうアプローチの是非も含めて言葉をかけてくださるので、それはむしろ答えそのものを与えられるよりも自分のためになったなと思うんです。そういうのって、きっと“敢えて”なんですよね?
鶴岡 多分ね(笑)。だって福山って、思考回路にもまったく淀みがないよね?
福山 迷うのがあんまり好きじゃないので、意識的にそう割り切ってしまっている感じですね。
鶴岡 そう、だからこそそこに少し深みや厚みを加えたいと思ったときにはどうすればいいかっていうと、福山の中で完成されているプランに対して淀みを与えて、「ん?」って考えてもらうしかなかった。
福山 具体的なディレクションをもらっていたら体裁を繕うことしかできなくなっていたような気もして、理解するのに時間はかかりましたが、すごく感謝しています。
(福山潤『声優MEN』で音響監督の“恩師”とプロ論交わす「∀ガンダムのキースは二度とできない」
※『声優MEN』VOL.17 「福山潤のプロフェッショナルトーク」連載第2回 ゲスト:音響監督・鶴岡陽太(2020/4/16)59〜60p)
(2ページ目) 福山潤『声優MEN』で音響監督の“恩師”とプロ論交わす「∀ガンダムのキースは二度とできない」 | ふたまん+
鶴岡さんは「誠意を持て」という当時の指示について、その意図を解説してくれている。
ここでの「誠意」とはおそらく、用意したプランや言葉をそのまま割り切って自動的に形にしてしまうのではなく、
あたかもその場で考え、淀みながらも相手と掛け合いをする中で、リアルタイムに紡ぎ出すような演技のことだったのだろう。
また、その淀みを口先や技術で完全に隠すのではなく(福山さんはそれができてしまうからこそ)、
その迷いも相手に見える状態にしたままでコントロールしながら芝居していく、相手そのものと相対する、そういう態度のことだったのだろう。
もうひとつの「勝算はあるのか」についても、福山さんの言う「体裁を繕う」ではなく、
ロジックを元に着地点を見据えた、自分なりの勝ち筋が、演出家や視聴者に伝わるような芝居を示唆するものだったのかもしれない。
鶴岡さんの、具体的ではないが役者に考えさせるタイプのディレクションについては、他にも証言がある。
『魔法少女まどか☆マギカ』の中でも、主人公まどかを演じる悠木碧さんに、次のようなヒントを出したという。第9話、まどかに対してキュゥべえが、家畜の屠殺のイメージを見せるシーンでの演技について、オーディオコメンタリーから抜粋する。
悠木 そう、なんかでも今のこのキュゥべえと対話してるシーンてすごい実は鶴岡さんと話してたりとかしてて、なんかそうキュゥべえに対して敵意を向けてるんじゃなくて、自分と葛藤して、っていう風に言われてて、なるほどぉ!と思って、でも! キュゥべえが淡々としてるから、私自身はどんどんキュゥべえにムカついていくっていう!
(略)
斎藤 まどかは知らないから抑えて、とかなってたよね
悠木 そうそう、まどかは誰かに対して恨みを向ける(こと)を知らないから、なんかそれに対してそんなに戦わないでっていうのがあって、すごいこう、私自身も葛藤しました(笑) 意外とこだわりのシーンだったりとか…。そう、「痛い」の方向が、攻撃じゃなくて「自分が痛いんだ!」って、なる、だけというのが
斎藤 そうそう、どんどん抱えていくんだよね、まどかは
悠木 そうなんですよね
鶴岡さんはここで、たとえば「もっと声を低く、語調もゆっくりさせて」という風な指示を出すことも可能だったろう。
しかし実際は「自分と葛藤して」というヒントを出すに留めることで、「中身的にはこういうことなんで考えて辿り着いてください」、つまり具体的なアプローチについては役者に一任しているようだ。これによって役者のキャラクターへの理解は悠木さんの中でも深まっているように見える。
鶴岡さんが視聴者に届けたい「作品の持つ面白さ」へ向かうためのヒントを役者に出すことで、鶴岡さんはじめメインスタッフが共有しているところの作品コンセプトを役者と共有することが、役者から高いパフォーマンスを引き出すために必要なのだろう。鶴岡さんは講演会の中で、この部分を次のように説明する。
僕が彼ら役者の演技に対してディレクションする場合、その面白さの「方向性」だけを伝えている。そのため「指示がよく分からない」と言われることも多いが、(役者の)個性を尊重したい。僕は再現性をもってできることが、客にも伝わると思っている。
録音物としてのアフレコ1:再現性のあるもの、絶対値で揺るぎのないもの
鶴岡さんも「(語尾の上げ下げまで指示していたら)局面局面においてね」と言っているが、そのキャラクターのセリフ全てに語尾の上げ下げを指示するのは、まず現実的ではない、時間がかかって仕方ないからだ。また、細かい指示の微調整でその場を切り抜けたとしても、作品監督・音響監督の目指す方向性が伝わっていなければ、以後の演技と方向性が相互に矛盾してしまうこともあるだろうが、これも避けることができる。
目指すゴールのイメージを共有することは、個性を発揮してもらうことが時間の節約にもなるということもあるが、それは役者へのリスペクトである。と同時に、その方法が役者のポテンシャルを発揮させ、作品全体の深みを増すことに繋がるのだろう。
もうひとつ注目したいのは「再現性を持たない表現は視聴者に伝わらない」という発言だ。これについては続く引用で、鶴岡さん自身の言葉で説明してもらおう。
沢城:観客側に回り過ぎるととてもできない温度の子(キャラクター)たちもいるけど、やっぱそっちに回り過ぎちゃうと、「私は終わったあと気持ちよかった」けど、果たして観た時にそれが100%伝わるのかっていうと、やっぱ違うなと思うと、あーやっぱ技術は必要ですねっていうとこにまた戻ったり。
鶴岡:うん、うん
沢城:そうなんですよね。でもなんか心ひとつの、バーッって言った台詞が胸を打つような時も、受け手側として、相手役として胸を打たれたこともあったりするので、でもまたこれが不思議なのが、スタジオですごく良かった台詞が、けして劇場で素敵だったりするわけでもないという……。どこでそのマジックがかかってるのか教えて!……ていう
鶴岡:やっぱりさ、そこのあとで色んなさ、100パーのものが最終的なところまでさ、保てないんだよ。たとえば機械を通ったりさ、出せる音量とか他の音の要素とか、あって。
けしてさ、それが生(き)のまま100%のまま出るわけではないから。そうした時に多分ね、そこで失われてしまうもの……こそが全てだったりすると、そのプロセスを経てしまうと何も残らなくなってしまった、残念……! みたいな。……まぁ、よくあるけどね。(ぼそっ)
沢城:そうですか(硬い声)
鶴岡:たとえばホラ…、「テスト良かったのにね?!」みたいな
沢城:あー!
鶴岡:あれはね…「それね、みんなファーストインプレッションだからだよ」みたいな
沢城:そうですね! あー、それはそうだな……
鶴岡:「それじゃなければ伝わらないもの」って実は……、ま、特に俺らのジャンル? 録音物? 録音物においては、「それじゃなければ伝わらないもの」ってのは最後までそれを維持できるかっていうと、ちょっと疑問なとこもあったりして……。そうじゃなくて、「絶対値で揺るぎのないもの」ていうのが無いと、最終的に作り上げる時にね、ひょっとしたら、そこだけに頼ってるといけないかも
(沢城みゆきと12の夜 #11 (2010/05/08))
アフレコは「ナマモノ」である、という鶴岡さんの意識は間違いない。
しかし一方で鶴岡さんは同時に、自身の手掛けるジャンルを「録音物」だと言う。
録音物というメディアを通して視聴者に役者の演技を届ける以上、色々な工程、たとえばアフレコのあとのダビングや編集といった段階で、アフレコの現場にあった「ナマモノ」のうち、幾らかの要素は抜け落ちてしまうということだ。
たとえば演技にBGMがオーバーラップさせられたり、放送用に映像の長さやタイミングを変更する編集作業の中で演技の呼吸が変えられてしまったり、ということだ。それでなくても、生身の人間が目の前で演じている時の身振りや熱気は、音声データには収めることができない。
鶴岡さんはそういう作業の各工程の中で抜け落ちてしまう可能性のあるものは、視聴者に伝わらない可能性があるという。だからこそ「絶対値で揺るぎのないもの」つまり、表現すべきものへの指向がハッキリした表現が求められると結んでいる。
それは鶴岡さんが、作品の面白さ・コンセプトへのアプローチについては、その具体的なやり方は任せていることとも関係があるだろう。つまり小手先の微妙な動きではなく、身体全体の動きが総体として目的に向かうような、パラメータの絶対値が高い表現を導くのが、役者と一緒に考え、目的地を共有する、鶴岡さんのディレクションなのである。
ナマモノとしてのアフレコ VS 工学的録音物としてのアフレコ
ここまで話してきたが、鶴岡さんの根底にあるのはむしろ、録音物の限界という考えなのではないかと思っている。音響監督が最終成果物を編集するのではない以上、細かいあれやこれやにコストを割くのではなく、色々な工程の中で失われない、コンセプトとして揺るぎないものに注力することが大切だという意識だ。
その一方で、そのような意識はアフレコの中で役者から、自分の持っているコンセプトとそのプランを超えるパフォーマンスを引き出すための、攻めの姿勢でもある。鶴岡さんは役者が提示してくる演技を元に、当初のプランを柔軟に修正していく。それは役者の個性へのリスペクトであるが、何より作品の面白さを先鋭化させるために、役者の演技に対してBGMやSEの演出のベクトルを揃えていくことでもある。今やこれを「ベストテイクを降ろすための技術」と言ってもいいだろう。
このとき、役者の演技が作品の面白さに適っているのかどうかを判断し、OKを出すのは、音響監督の責任である。そこでは、役者にベストの演技をさせるためのディレクションとはまた違う、自分の責任において作品解釈の方向性を定める、いわば度胸のようなものも必要になってくる。
しかしそれは音響面の責任者である音響監督に求められる、大切な力・素養でもあるということだ。
最後に:音響監督の音響演出について考えることは可能か?
本稿の前半ではダビング、後半ではアフレコという作業の具体例から音響監督、特に鶴岡陽太さんの特徴的な音響演出・ディレクションについて触れてきた。
鶴岡さんの音響演出には、作品の持つ面白さ・コンセプトをどのように表現するか、という一本通った軸がある。これに沿って鶴岡さんの発言を読み解くことで、ダビングやアフレコといった別工程においても、その軸は鶴岡さんの中で揺らいでいない。
音響監督という役職については、アニメファンの中でもあまり知られていない部分が多い。実際、僕も本稿を書くにあたって、資料を集めるのにかなり時間がかかってしまった。しかし、今回提示してきた材料は自分でも非常に興味深いものが多かったように感じる。
少なくとも、鶴岡さんは2010年周辺のアニメを語る上で、最も欠かせないスタッフのうちの一人であることは間違いない。これ以降、特に鶴岡さんひいては音響監督に関する言及は多くなって欲しいと強く願っている。
最後に、鶴岡さんが音響という仕事に対する態度とその未来について、
「スタンダード」という言葉を使って明確に語ってくれている箇所を抜粋したい。
福山 (編略)すごいスピードでデジタル化しつつあるいまの環境で、次の世代に何をどう伝えていけばいいのかっていうのは僕らの世代が直面している課題だと思うんです。
鶴岡 だからこそ常にスタンダードを示し続けることが大切なんじゃないかなと思うけどね。
福山 スタンダード、ですか?
鶴岡 そう。私なんかはもう60歳だけど、やっぱり20年くらい前までは毎日スタジオで何かを追求していたと思うよ。音響技術にしても、それまでは劇場版でしかできなかったようなことが深夜アニメでもやれるんだということを示してきた日々だった。やっていることは役者さんと全然違うけど、私にとっての「スタンダードとは何か」ということの模索の日々だったんだよね。スタンダードとは、その時代ごとの技術と先人の知識が積み重なり、自分の中に基準として作られるもの。つまり、いつの時代でも大事なのは自分にとってのスタンダードを言葉や振る舞いを通して、次の世代に指し示していくことだと思う。
(福山潤『声優MEN』で音響監督の“恩師”とプロ論交わす「∀ガンダムのキースは二度とできない」
※『声優MEN』VOL.17 「福山潤のプロフェッショナルトーク」連載第2回 ゲスト:音響監督・鶴岡陽太(2020/4/16)61p)
(3ページ目) 福山潤『声優MEN』で音響監督の“恩師”とプロ論交わす「∀ガンダムのキースは二度とできない」 | ふたまん+
鶴岡さんにとっての「スタンダード」とは、時代によって外側から既に決められており、それに従っていれば安心なものではないという。
むしろ過去の蓄積からの押し上げや、技術進歩の足早な歩みの中、自分なりの絶え間ない模索により、自分の内側にこそ育つものこそが「スタンダード」なのだと。
それはアニメ音響という分野で鶴岡さんが常にトップランナーの開拓者であったことの自負であり、
またそれを自分の内側だけでなく、次の時代のあるべきスタンダードとして、
多くの音響関係者へ言葉と態度を通じて伝えていくことを諦めることのなかった、鶴岡さんの信念のことだと感じた。
鶴岡さんの今後のますますのご活躍を願って、本稿を閉じる。読んでくれてありがとう。
関連記事
*1:この観点から補足すると、制作進行という役職は、全てのカットの進行状況に責任を負う、実写作品で言えば助監督にあたる
*2:映像が「保たない」とは、一般に、時間単位での映像の面白みや情報量が少なくなり、視聴者を退屈させ、映像作品に対する集中力を欠かせてしまう状態
*3:このライトノベル主人公の特徴的な態度は、後年『僕は友達が少ない』シリーズで痛烈に再批判される
*4:鶴岡音響監督との代表的な仕事として、『ぱにぽに』シリーズ:レベッカ宮本、『物語』シリーズ:戦場ヶ原ひたぎ、『ダンスインザヴァンパイアバンド』:三枝由紀など
*5:少しマニアックな回り道になるが、更にこのシーンの経緯を検証しておこう。上記書籍掲載のこのシーンの絵コンテ(担当は笹木信作さん)時点で「……ッ!!」「・・……ッ!!」「ぐぅ…… ・・・…ッッ!!」「まどかっーーーッ!!」というほむらのうめき声と叫びが追加されている。しかし笹木さん本人もしくは新房昭之監督によって、最後の「まどかっーーーッ!!」というカットは欠番となっている。結果、拳銃のマズルフラッシュだけが光り、暗転するという最終的な描写に落ち着いた。(なお、出演者にはアフレコに際し、脚本最終稿ではなく、絵コンテのセリフを書き起こした台本が配布されている。絵コンテ段階でストーリーやセリフが変わることは多い
*6:鶴岡音響監督との代表的な仕事として、『荒川アンダーザブリッジ』シリーズ:マリア、『物語』シリーズ:神原駿河、『ローゼンメイデン』シリーズ:真紅など





